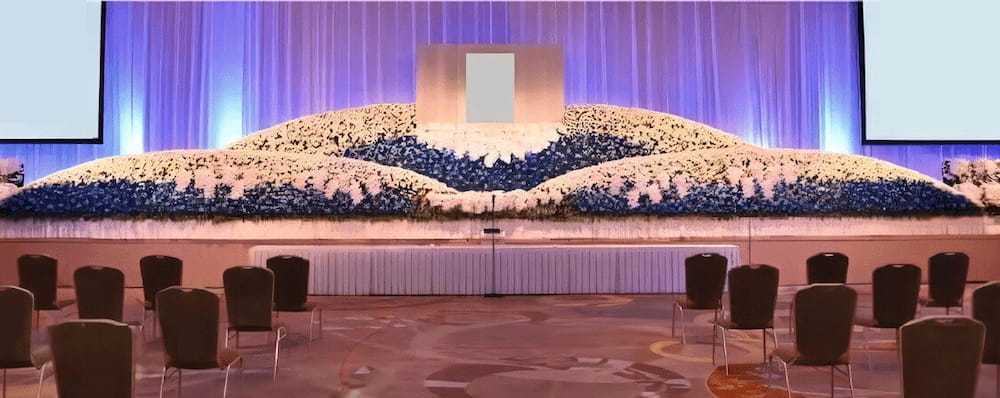- 社葬・お別れの会・合同葬ならセレモア
- 社葬の知識
- 社葬・お別れの会の基礎知識
- 事業承継のリスク管理は「社葬取扱規程」から|税務も安心のテンプレート付
事業承継のリスク管理は「社葬取扱規程」から|税務も安心のテンプレート付

「事業承継を考え始めたが、何から手をつければいいのか…」 会社の未来を想う経営者様ほど、その責任の重さから漠然とした不安を感じていらっしゃるかもしれません。特に、ご自身に万一のことがあった場合のリスク管理は、後回しにしがちなテーマです。
しかし、会社の未来を守るリスク管理と円滑な事業承継の第一歩が、実は「社葬取扱規程」の整備にあることをご存知でしょうか。
この規程は、「縁起でもない」と敬遠されがちですが、その本質は、会社の混乱を防ぎ、税務上の問題をクリアにし、後継者がスムーズに舵取りを始められるようにするための、極めて重要な経営戦略です。
本記事では、事業承継とリスク管理の観点から「社葬取扱規程」の重要性を解き明かし、具体的な作り方からテンプレート、専門家が回答するFAQまで、経営者の皆様が今すぐ行動に移せるよう、分かりやすく解説します。
事業承継に「社葬取扱規程」が不可欠な3つの理由|経営者のためのリスク管理術
平時のうちに整備する「社葬取扱規程」は、有事の際に会社を守る強力な盾となります。ここでは、事業承継におけるリスク管理の観点から、その3つの重要な役割を解説します。
1. 【リスク管理①】突然の混乱と対立を防ぐ「羅針盤」
規程がなければ、逝去後の限られた時間の中で「誰を対象とするか」「費用はどこまで会社負担か」といった判断を、その場の感情や力関係で決めざるを得ません。これは役員間の対立や、会社と遺族との間に溝を生む大きなリスクです。規程は、客観的で明確な意思決定の基準となり、組織と遺族を無用な混乱から守る防波堤となるのです。
2. 【リスク管理②】税務調査で否認されない「法的根拠」
社葬費用は、社会通念上相当な範囲であれば「福利厚生費」として損金算入が認められます。しかし、明確な根拠がなければ「役員への個人的な利益供与」とみなされ、追徴課税のリスクが生じます。規程によって会社負担の範囲を明記することは、経費の正当性を証明し、会社の資産を守る極めて重要な「証拠」となります。
3. 【事業承継の円滑化】後継者のリーダーシップを示す「舞台装置」
規程の中で「葬儀委員長は後継者たる代表取締役社長が務める」と定めておく。この一文が、社葬の場を新体制の公式なお披露目の舞台に変えます。故人の遺志を継ぐ覚悟を内外に示し、後継者のリーダーシップを自然な形で印象付けることで、円滑な事業承継に不可欠な従業員や取引先の信頼を醸成します。
規程に盛り込むべき必須8項目|事業承継のリスク管理視点で解説
規程を作成する際は、以下の8項目を網羅することが一般的です。事業承継とリスク管理の視点から、自社の実情に合わせて内容を検討してください。
社葬取扱規程に盛り込むべき必須8項目
| 条項 | 概要とリスク管理上のポイント |
|---|---|
| 第1条:目的 | 会社の功労者に報いると同時に、有事の際のリスク管理を目的とすることを明記します。 |
| 第2条:適用範囲 | 対象者を明確にし、判断のブレによるトラブルリスクを回避します。「創業者」「代表取締役」に加え、「取締役会が認めた者」という条項で柔軟性を持たせます。 |
| 第3条:社葬の決定 | 「取締役会の決議」と定めることで意思決定プロセスを明確化し、ガバナンス上のリスクを軽減します。 |
| 第4条:葬儀の形式と執行体制 | 葬儀委員長を「後継者たる代表取締役社長」とすることで事業承継を社内外に公式に示す重要な役割を担います。 |
| 第5条:会社が負担する費用の範囲 | 税務リスクを回避する最重要項目です。「社会通念上」等の曖昧な表現を避け、具体的な項目を列挙します。 |
| 第6条:遺族との役割分担 | 会社と遺族の負担範囲を明確化し、金銭トラブルのリスクを未然に防ぎます。 |
| 第7条:弔慰金の支給 | 社葬とは別に弔慰金を支給する場合の根拠となります。詳細は別途「弔慰金規程」で定め、事業承継後の遺族への配慮を示します。 |
| 第8条:付則 | 施行日と改廃手続きを定めます。経営状況の変化に対応できるよう、定期的な見直しがリスク管理上重要です。 |
【コピーして使える】社葬取扱規程テンプレート(事業承継・リスク管理対応版)
以下は、事業承継とリスク管理の観点を盛り込んだテンプレートです。貴社の実情に合わせ、専門家と相談の上でご活用ください。
社葬取扱規程
| 条項 | 概要とリスク管理上のポイント |
|---|---|
| 第1条(目的) | この規程は、株式会社◯◯(以下「当社」という)の発展に著しく貢献した者が逝去した際、その功績を偲び、会社の品位を保ちつつ、社葬を円滑に執り行うことで有事の経営リスクを管理し、安定した事業承継に資することを目的とする。 |
| 第2条(適用範囲) | 本規定の適用対象者は、次の各号に掲げる者とする。 (1)当社の創業者 (2)当社の代表取締役社長および会長 (3)在任中に逝去した取締役および監査役 (4)その他、取締役会において、会社の発展に対する功績が特に顕著であると認められた者 |
| 第3条(社葬の執行) | 社葬の執行は、取締役会の決議をもって決定する。 |
| 第4条(葬儀委員長) | 社葬の葬儀委員長は、原則として代表取締役社長が務める。これは、円滑な事業承継を社内外に示すための一貫とする。ただし、代表取締役社長が故人である場合等は、取締役会の決議により別途定める。 |
| 第5条(会社負担の適用範囲) | 会社が負担する社葬の費用は、社会通念上妥当と認められる範囲とし、以下の各号に掲げる費用とする。税務上のリスクを回避するため、その範囲を明確に定める。 (1)葬儀の企画・運営に関する費用(会場費、祭壇設営費、遺影作成費等) (2)死亡広告、会場礼状等の印刷費および通知に関わる費用 (3)会葬者に対する返礼品費用 (4)その他、取締役会が社葬に必要と認めた費用 |
| 第6条(遺族との分担) | 香典、供物、戒名料、仏壇・墓石の購入費用、法要に関する費用等、個人的な儀礼にかかる費用は、遺族の負担とし、会社と遺族間のトラブルリスクを避けるものとする。 |
| 第7条(弔慰金) | 対象者の遺族に対し、別途定める弔慰金規程に基づき弔慰金を支給する。 |
| 第8条(規程の改廃) | 本規程の改廃は、取締役会の決議によるものとする。経営環境の変化に対応するため、定期的に見直しを行うものとする。 |
| 付則 | この規程は、◯◯年◯◯月◯◯日より施行する。 |
社葬・事業承継のリスク管理に関するFAQ
Q1. やはり生前に作るのは縁起が悪い気がします。
A1. お気持ちはよく分かります。しかし、これはご自身の功績にふさわしい形で会社と遺族に感謝される環境を整える、未来への投資です。事業承継を成功させるための重要なリスク管理であり、経営者として最後の責任と捉えるのが適切です。
Q2. 規程作成は専門家に相談すべきですか?
A2. はい。最終的には弁護士や税理士によるリーガル・タックスチェックを強く推奨します。本記事のテンプレートで骨子を固めてから相談すれば、効率的に進められます。これもリスク管理の一環です。
Q3. 経費負担の範囲はどこまで細かく決めるべきですか?
A3. リスク管理の観点からは、可能な限り具体的に列挙すべきです。「社会通念上」という言葉だけでは解釈の余地が生まれ、税務調査での指摘や遺族とのトラブルのリスクになります。
Q4. 一度作成した規程は見直す必要がありますか?
A4. はい。経営体制や社会情勢の変化に対応するため、3~5年に一度、または経営陣の交代など事業承継の節目で見直すことが、効果的なリスク管理に繋がります。
Q5. 社葬を行わない場合、この規程は不要ですか?
A5. 社葬を行わない選択も有効なリスク管理です。その場合でも、「弔慰金規程」の整備は強く推奨します。功績に応じた弔慰金のルールを定めておくことで、事業承継後の遺族への感謝を示し、会社として経費計上することが可能になります。
【次のステップへ】事業承継・リスク管理の個別相談会
「社葬取扱規程」は、事業承継におけるリスク管理の重要な第一歩です。
「自社に最適な規程の具体的な内容を知りたい」 「事業承継全体の流れと、今すぐ着手すべき課題を整理したい」 「税制や法改正を踏まえた、専門家のアドバイスが欲しい」
このような経営者様のために、私たちは事業承継と企業のリスク管理を専門とする、個別相談会を随時開催しております。貴社の状況に合わせた、具体的な次の一手をご提案します。
まとめ:未来へのリスク管理こそ、最高の事業承継
「社葬取扱規程」の整備は、決して後ろ向きな作業ではありません。それは、創業者が築き上げた会社を盤石にし、次の世代へと思いを繋ぐための、現経営者にしかできない極めて前向きな経営判断なのです。
万一の事態というリスクに備え、冷静な判断ができる平時のうちに手を打っておく。その積極的なリスク管理こそが、従業員や取引先、そして最も大切なご遺族を守り、円滑な事業承継と企業の持続的な成長を支える礎となります。
この記事が、貴社の未来を守る確かな一歩となれば幸いです。